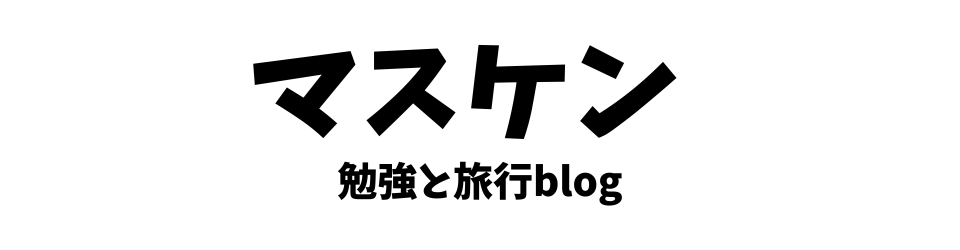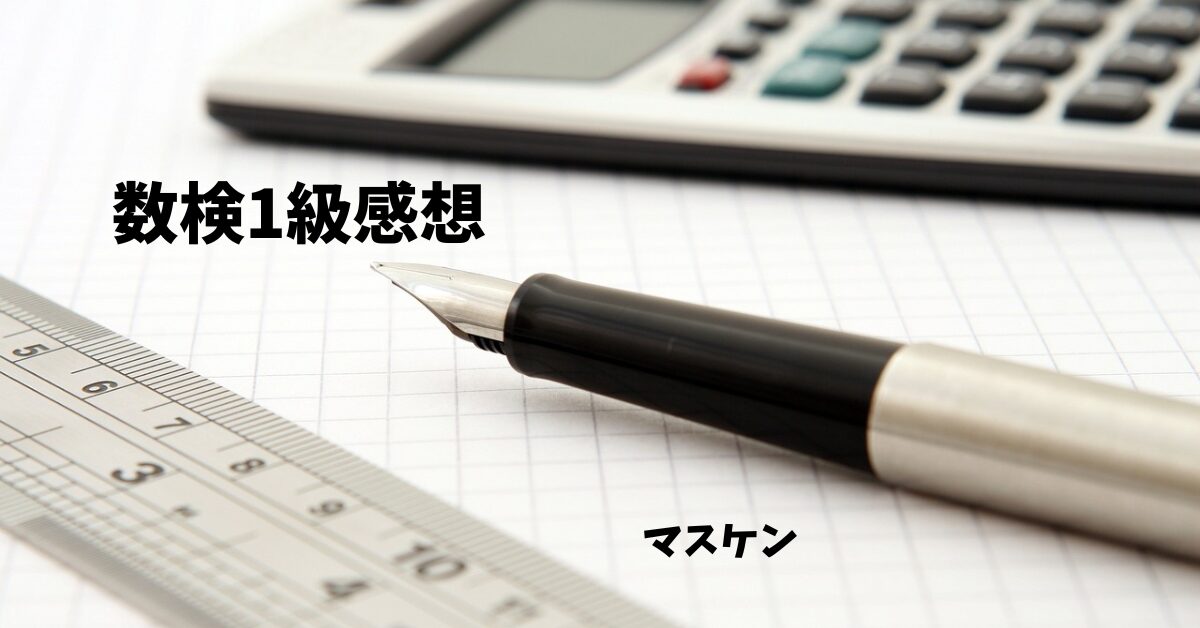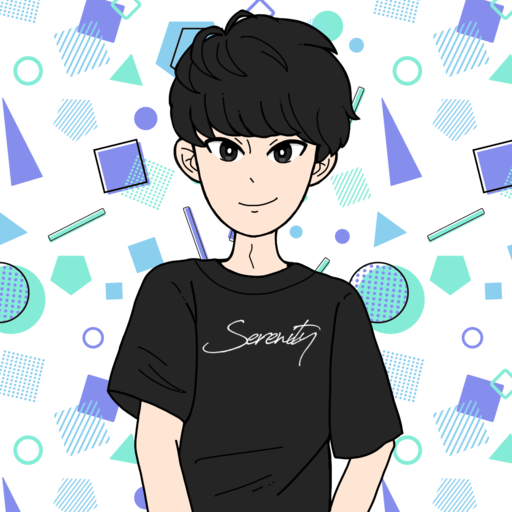こんにちは、マスケンです!
今回は僕が独学で数検1級に挑んだときの体験談をまとめています。

数検1級に挑戦してみたい!
そして合格したい!
という方は是非最後まで読んでみてください。
この記事を書いた人
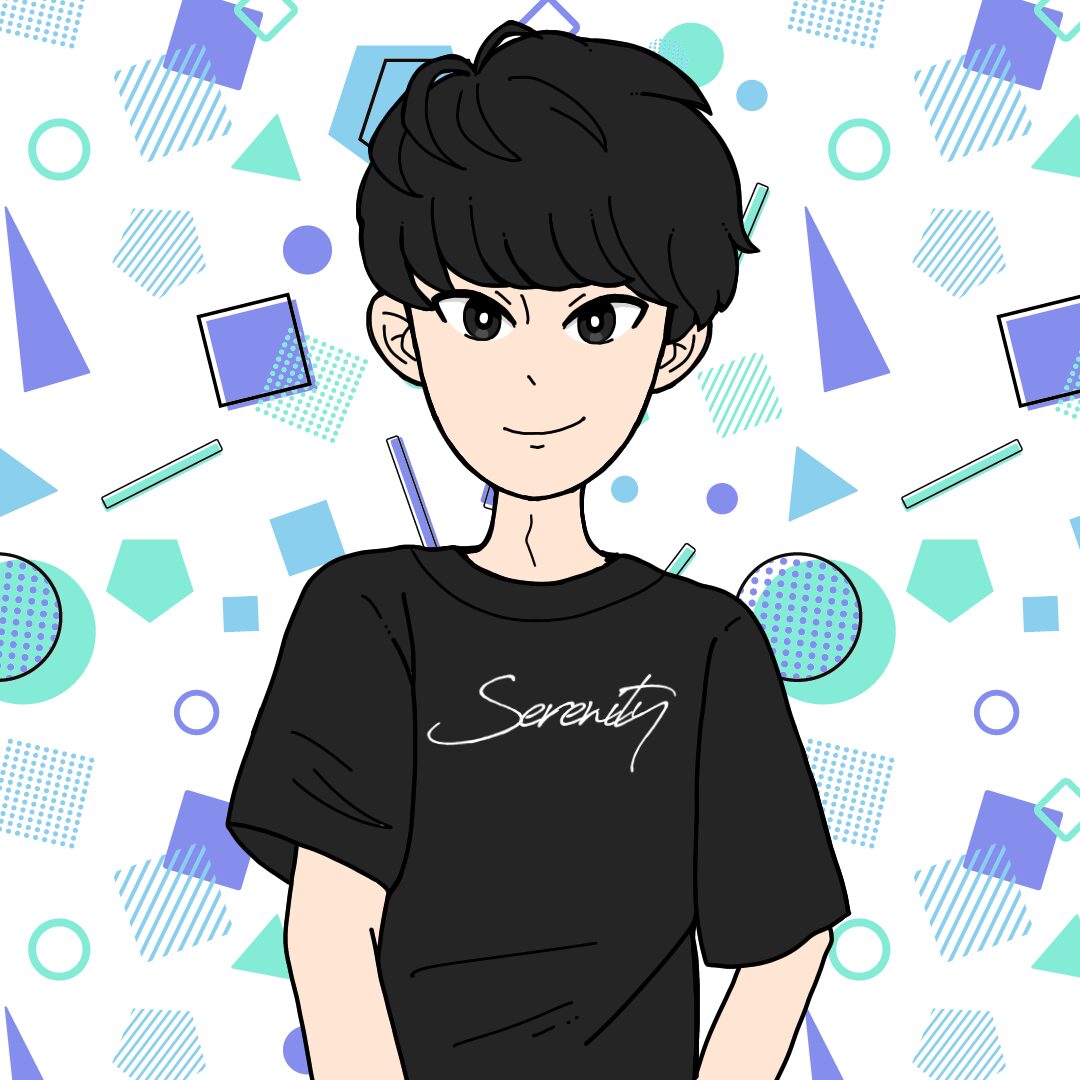
マスケン
(@mathkenblog)
- 慶應義塾大学在学中→東大大学院進学予定
(在学の傍らブログ活動中) - 様々な資格を短期間で取得
(簿記2級を50時間、FP2級を30時間、TOEIC835点を1週間など) - 大学生で旅行回数10回以上
(長期休暇中は必ずどこかへ旅行しています)
この記事を書いている僕はブログ歴2年の大学生ブロガーです。大学受験で得た知識や、現在の大学生活、趣味の旅行について発信しつつ、日々自己研鑽しています。
はじめに:数検1級を受験したきっかけ

僕は大学受験の浪人時、数学が非常に得意になりました。
そのため、その知識を活かして資格をとりたいな、と思ったのが始まりです。
そこで見つけたのが数検1級。

せっかく数学が得意なんだし、数学最高峰の資格をとりたい!
と強く思うようになりました。
数検1級の範囲
数検1級の範囲は多岐に渡ります。
【解析】 微分法、積分法、基本的な微分方程式、多変数関数(偏微分・重積分)、基本的な複素解析
引用:数学検定1級
【線形代数】 線形方程式、行列、行列式、線形変換、線形空間、計量線形空間、曲線と曲面、線形計画法、二次形式、固有値、多項式、代数方程式、初等整数論
【確率統計】 確率、確率分布、回帰分析、相関係数
【コンピュータ】 数値解析、アルゴリズムの基礎
【その他】 自然科学への数学の応用 など
このなかで、高校範囲で解ける問題は「微分法」「積分法」「初等整数論」くらいです。
残りは大学数学範囲です。
勉強スタートしたのは2週間前
なんと、数検1級の勉強をスタートしたのは2週間前です。
(めちゃくちゃ舐めてますね…)
数検1級の勉強をし始めたときどのような状態だったのかというと…
高校数学はマスターしていた
僕は塾講師として高校数学を教えていたためあまり忘れていませんでした。
そのため、受験からかなりの期間が経っていても、高校数学はできる状態をキープしていました。
壁となった線形代数、微分方程式
その一方で、「線形代数(行列)」「微分方程式」といった大学範囲の数学の勉強が大変でした。
大学1年生のときに一応学習はしました。
しかしほぼ覚えていなかったため一からのスタートとなりました。
大学範囲である微積分や線形代数は、慶應の教科書を使いました。
というのも、慶應の教科書、結構分かりやすいんです…
独学でも理解が進みました。
とはいえ、慶應の教科書は買えませんよね。
そこでおすすめなのが、「数検1級準拠テキスト」です。
(僕も線形代数は購入しました)
特に線形代数は、これ1冊で1次にも2次にも対応できます。
なお、微分積分では微分方程式がありません。
微分方程式の対策としておすすめなのが「マセマ常微分方程式」です。
この本は大学数学で出てくる常微分方程式をまとめています。
院試対策でやったのですが、かなり有用でした。
また、統計分野は「統計的データ解析の基本」を使いました。
こちらも大学で使用した教科書であり、統計分野の頻出分野である
「正規分布」「t分布」「χ2分布」「F分布」
の練習問題を解けました。
また、数検特有の問題を知るために「出題パターン徹底研究」も購入。
とはいえ、独学ではなかなか厳しく、過去問に入るまでに1週間かかりました…
この1週間はほとんど予定がなかったので、受験生さながらの生活を送っていました。
1週間前からスタートした過去問
過去問として「完全解説問題集」を利用しました。
(数検が唯一発行している問題集です)
2012年から2014年までの7回分の過去問を収録していますが傾向を知るうえで非常に役に立ちました。
1次の問題は全て解けるようにしました。
2次の問題は自分が本番解くであろう「統計分野」「整数問題」
そして、必答である「線形代数」「微積分」を解けるようにしました。
本番1週間前から過去問をスタートしたのですが、既に大学の授業は始まっており、上手く両立させて勉強しました。
もっと早くから対策すべきです
僕は2週間前からなどという非常に遅いスタートを切っています。
ただもちろん、本来はもっと早く始めるべきです。
なぜ2週間前から始めたのかというと…
- 高校数学はほとんどマスターしていたから
- 大学範囲を学べる環境にいたから
このように、僕の数学に関する環境がかなり良かったため、2週間前からでも大丈夫かなと感じました…
かなり無謀ですね…
皆さんはもっとしっかり対策してください。
受験した感想
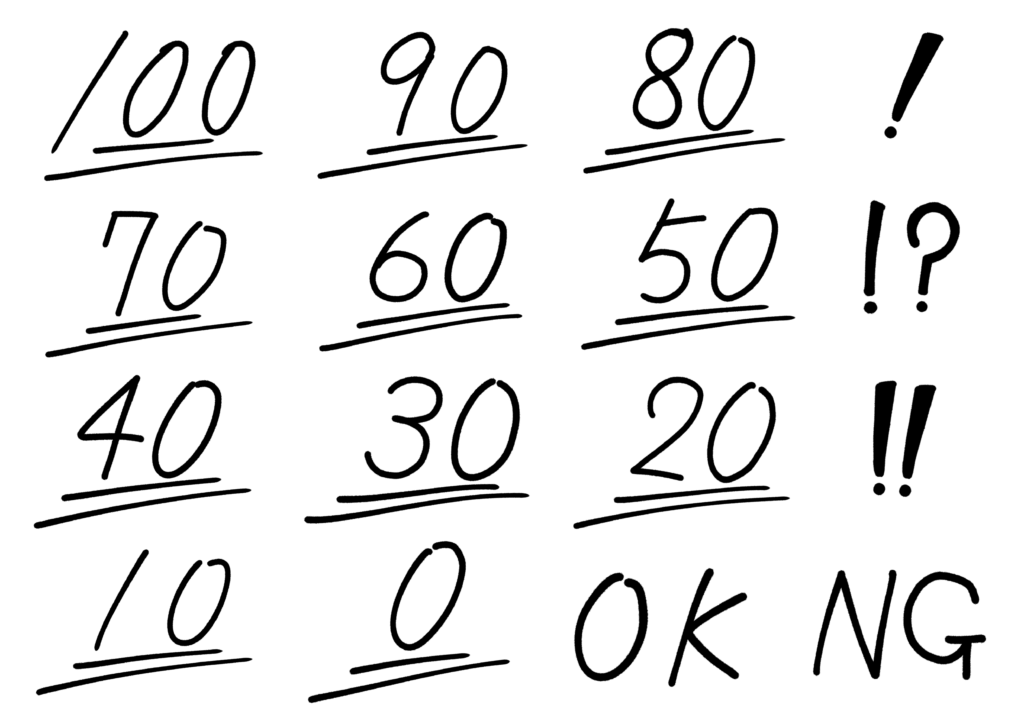
第423回検定(2024年4月14日)を受験してきました。
1級と準1級の人が同じ教室で、ともに30人弱いました。
問題を公表することはできないので、以下、感想になります。
1次
考えていたこと
過去問演習では7回中6回合格点に達していたので、そこまで緊張せずにスタート。
試験中に飲み物を置けるのは大きかったですね。
また、問題は透かし見ができました。
「計算ミスをするな」「答えが出たら確認しろ」
考えていたのはこれだけです。
時間配分
30分弱で6問を解き終わるまでいいペース。
最後の微分方程式の問題だけ、解き方が分からずてきとうに書きました。
そして、残りの25分ほどで1~6番までを注意深く見直ししました。
「計算ミスがなければ6点で合格してる!」
と思いましたね。
2次
考えていたこと
2次はうってかわって、過去問演習では2回しか合格点に達していなかったので、
「分かる問題出ろよ…」
と思っていました。
こちらも透かし見ができました!
選択問題は積分の問題である2番が解けそう…と透かし見したときに感じました。
さて、試験がスタートしたらまずは必答問題を確認。
6番は「直交行列」の定義を度忘れ。
とりあえず自分の思う定義で問題を無理やり解くことを決意。
7番は重積分の問題。これはいけそう!と心の中でガッツポーズ。
4番の統計問題を見ると「F分布」で、解き方に自信がなかったのでスルー。
もう1問の選択問題は5番を選択。2014阪大を思い出すような積分の問題でした。
結局選択問題は統計ではなく、高校数学で解ける範囲の2問を選びましたね(笑)。
時間配分
5を解く(20分)
2(積分)を解く(40分)
7(微積)を解く(60分)
6(行列)を考え抜く(90分)
2、5、7の見直し(110分)
2に戻り、適当に答案を書く(120分)
「6番以外はあっているはず…」と思いました。
受験結果

結果は…
1次合格でした。
| 1次 | 7点中6点 | 合格! |
| 2次 | 4点中2.2点 | 不合格… |
積分の問題である2番が勘違いにより0.2点しかとれていませんでした。
また、6番は最初から解法が間違っていたため、0点という結果に。
5番と7番は満点の1点で、合計2.2点という感じになりました。
合格点まであと0.3点…
悔しい結果となりました。
まとめ:早くから対策しよう。
いかがでしたか?
- 高校数学はほとんどマスターしている
- 数検1級の範囲を学べる環境にいる
この2つが前提にあるとしても、対策は早め早めにすべきです!
数検1級を独学で受験するか考えている方は、しっかりと参考書を揃えて挑みましょう!
その後の数検受験体験記
リベンジとして、第427回検定(2024年7月21日)を受験しました。
▼そのときの記事はこちら。
-
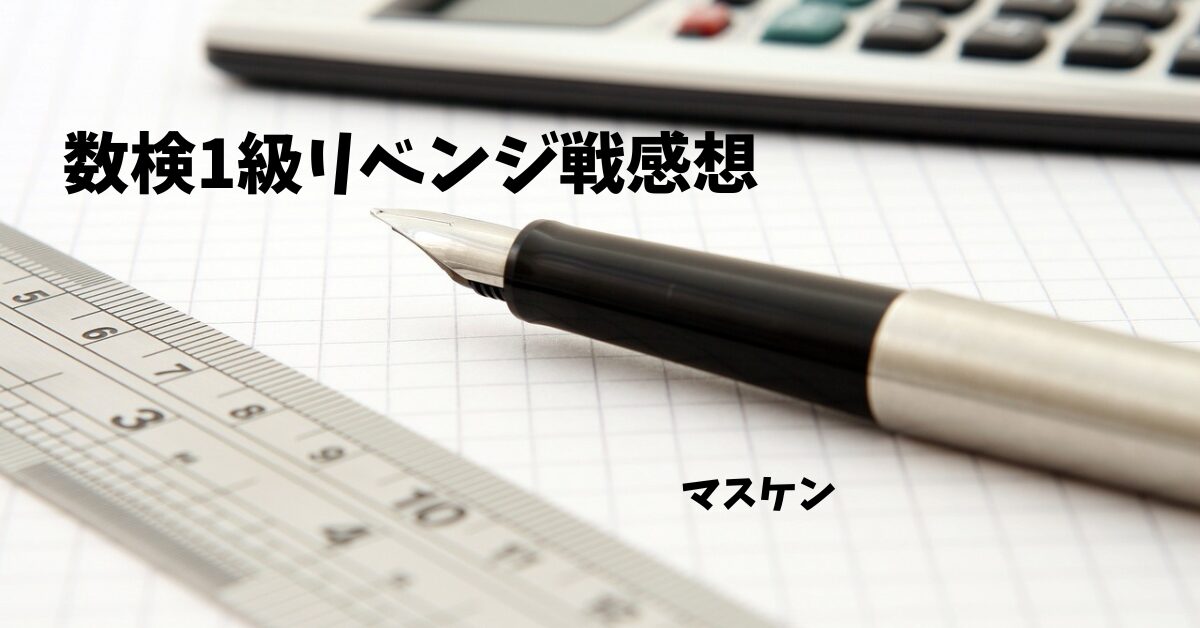
-
【2回目】大学生が独学で数検1級に挑んだときの体験談
今回は、大学生が数検1級をリベンジしたときに感じたことをまとめていきます。 なおこの回は不合格でした。悪しからず。 ▼僕が数検1級を初めて受けたときの感想はこちら。 ▼その後リベンジしたときの感想はこ ...
また3回目として第431回検定(2024年10月27日)を受験しました。
▼そのときの記事はこちら。
-
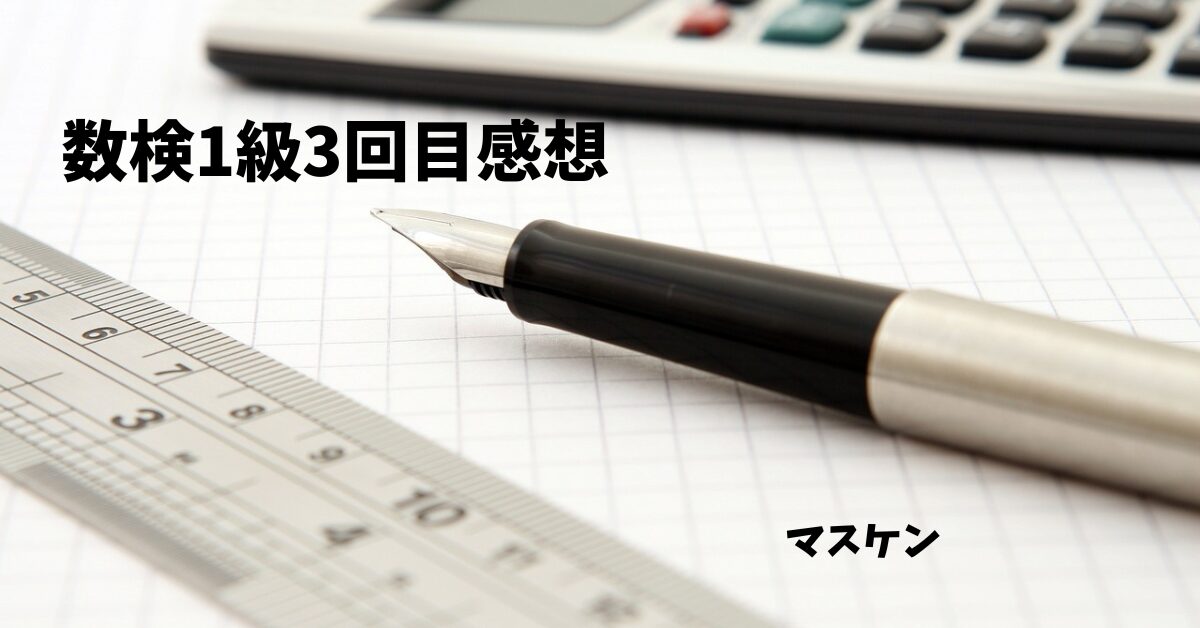
-
【3回目】大学生が独学で数検1級に挑んだときの体験談
今回は、僕が数検1級を受験したとき(3回目)に感じたことをまとめていきます。 ▼僕が数検1級を初めて受けたときの感想はこちら。 ▼僕が2回目に数検1級を受けたときの感想はこちら。 過去2回受験したとき ...